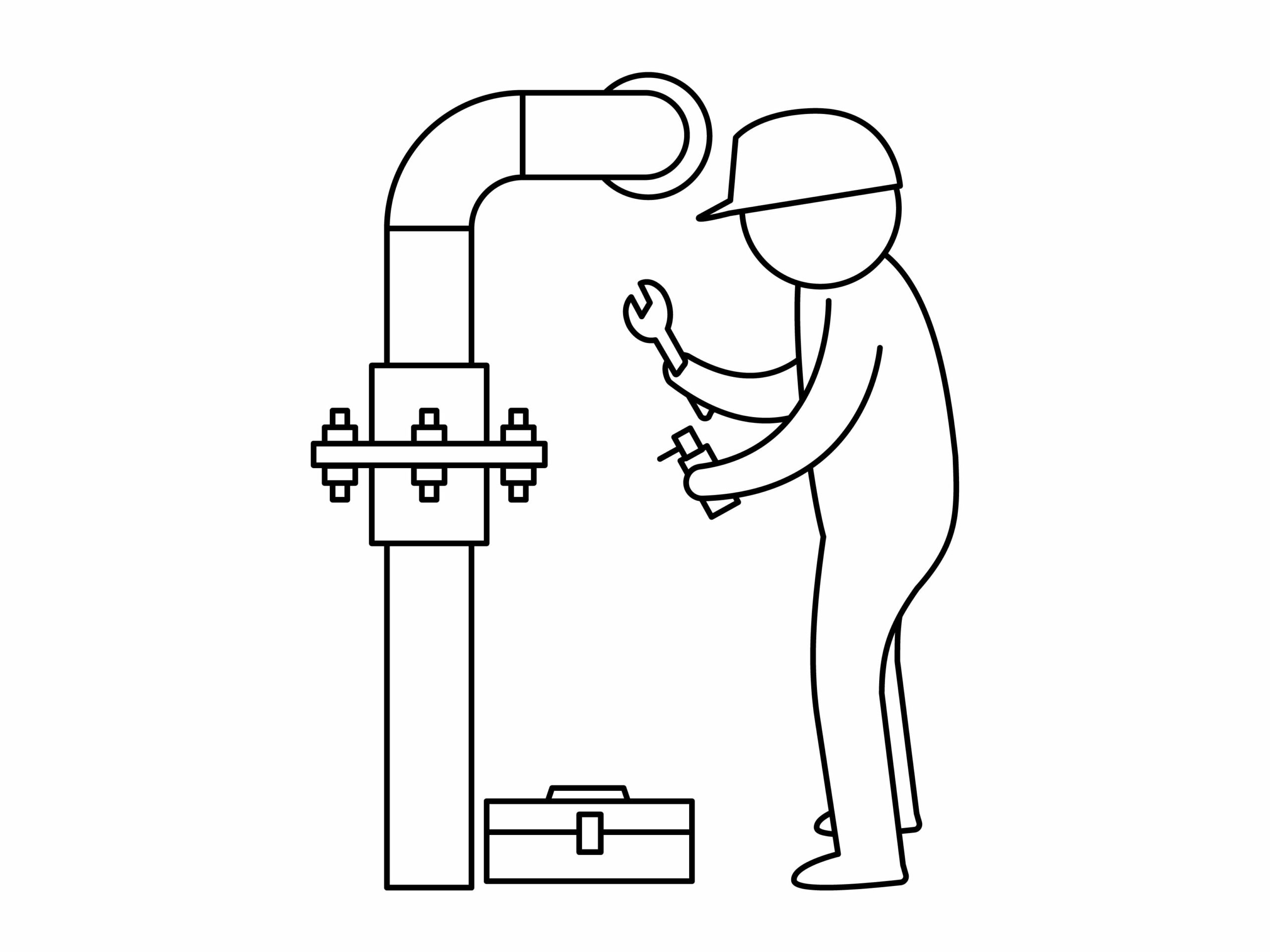
目次
配管工とコーダーは似ていた
「web制作」という言葉だけが独り歩きし、ビジネスとしての実態をつかめないまま勉強を続けていました。いざ営業まで進んで分かったことは下請け業者という仕組みはどこも同じだった。
配管工職長経験者が、価値あるコーダーとして認めてもらうためにはどうあるべきか。
という話です。
フリーランスコーダー=1人親方
建築業界の1人親方も、個人事業主でweb制作コーダーをやるのもビジネスの構図は同じです。
1人親方も「〇〇(苗字)設備」と名乗り、経理や営業活動しています。更に人を雇えば立派な会社です。
1次、2次会社とお付き合いし、現場の一部、専門的な部分を任されます。信頼を頂ければ何年間もお付き合いする関係になります。うちの管工事会社は消火設備会社数社と20~30年お付き合いがありました。
お金の大元であるお客さん(施主)が求めているのは建物そのものです。
しかし元請けの建築会社も各種設備・電気・内装まで自社でできる訳ではありません。蛇口も空調も電気もない、火災対策もない建物は誰も使ってくれません。そのため数多の専門職会社が集まって建物が完成します。
消火配管工がメインでも、親方ネットワークの繋がりによっては衛生配管や空調配管もお手伝いした事もありました。会社の信頼によってご紹介があり、繋がった時もあるかと思います。
これはコーダーも同じことです。大元のお客様が求めているのは自社の宣伝や売り上げアップといった結果ですが、そのための提案、その為のサイトを実現するのも多くの専門職で成り立っています。ディレクションやマーケターの方がコーディングまでするのは効率が悪いですし、機能実装まで行くとデザイナーの方でも苦戦するでしょう。
では専門職となんでしょうか?「コーディングができます」は専門職と言えるでしょうか。
実際に管工事であった事例
1次設備総合Y社、ステレンレス配管を始める
一般的に管工事は鉄管で行われます。管工事会社は旋盤を現場に設置し、図面と現場を見て必要であれば鉄管用の切断機(バンドソー)や旋盤を使いパイプを加工して仕事を進めていきます。
しかしY社は、職人が減ってきている背景や、業務効率化をすすめる為に「ステンレス配管」という商品を売り出しました。
あらかじめ図面で設計された寸法通りの配管が現場に山のように搬入されてきます。
両側にはフランジや接続継手が付いており、パッキンを挟んでボルトで締めていけば
「プラモデルのように誰でも簡単に組める」「どのパーツも後から外して交換できる」のが売りです。
(鉄管ねじ込みは切断でもしない限り途中から外せない)
歴戦の職人でなくても、素人でも水漏れなく配管していけるという考えです。
やろうとしている事はweb制作で言えばノーコードに通じるものがありますね。
作業に現場経験値は不要か?
しかし現実はそうはいきません。ステンレス配管は融通が利かないのです。
私も経験が浅かった頃は「形ができあがっているのでわかりやすい」と考えていましたが、周りの職人からは「面倒くさい、鉄管の方がいい」という声が聞こえました。
実際には壁や梁、他の設備配管と衝突する事があります。鉄管なら加工して済む事です。
図面が読めない人が配管した場合、図面と現場の違い、他の設備との兼ね合いなどに気が付きません。
「合わないからこうした」「図面通りだから」で済まないことも多々あります。
スプリンクラーだけでなく、同じ設備の衛生配管や空調配管のルールもある程度知る必要があります。
衛生排水は勾配が必要で1/100の角度で下がってくるので、この高さでは衝突する可能性がある。
空調エアコン機器の周りは点検口がありメンテナンスを行うので配管で邪魔してはいけない。ルートをずらすべきだ。
そういった周辺知識も必要です。
「スプリンクラーヘッドの警戒範囲が足りないから、配管の取り口を増やすべきだ。寸法書くから再注文して」「壁の陰に散水が届かない」といった事まで確認して説明したり
過去の経験から対策を考えどうすべきか報告までするのは経験の浅い人では難しいです。
軽量・天井ボードが張られてから事実に気が付き、直すのは絶望的となります。
※スプリンクラーヘッド=オフィスやデパートの天井に着いている、火災で散水される丸い器具。警戒半径2.3mや2.8mなどメーカーにより違いがある。
図面のミスで、それを作った2次設備会社のミスだったとしても、そこに気づいて対策を取るのが経験ある職人です。
最終的に建物が完成間近になると、消防署が来て消防検査を行います。
直しがあれば建物は使用許可が下りません。お金も出ません。苦しむのは作業した本人達です。
また、このY社のステンレス配管登場当初は、フランジやネジの部分が非常に漏れやすく、あろうことか水圧テスト時に継手溶接部分から水漏れするという未完成の技術でした。
職人達の努力でなんとか収まっていましたが、とても素人が組んで成立するものではありませんでした。
問題が現れた時真価を問われる
スピードや安さよりも、そういった想定外の問題に気づいた時どう対処するか。
時には2次、1次の監督さんも困り「何かいい道具や案ないですか・・?」と聞かれることもあります。
「監督」と「実作業をしている職人」では攻略してきた経験内容が違うのです。
この時「それはできません」「指示されてない」「教えてください」では仕事になりませんし、別の会社を呼ぶのも簡単ではないです。
高齢者で実務30年レベルのベテラン職人が呼ばれる理由もこういったところで、誰も想像もつかなかったローテク、古典的手法(ロープを使った配管吊り上げ)などで問題を解決することがあります。
「マジで?」「さすが・・〇〇さん・・」と自然に声が漏れ、経験者の風格で「あの人ならなんとかしてくれる」という印象が残ります。
webコーダーの価値は何か
デザインカンプ=図面を実装するもの
webコーダーは、工程で言えば最後の仕上げで、決まったデザインを動く形にする作業と言えば作業です。では作業と仕事を分けるのはなんでしょうか。
作業=自分ルールの一方的な結果の納品
仕事=双方連絡相談しながらできたより良い結果の納品、と考えます。
これは設備屋職長時代も同じことでした。
よくお困りごと、面倒ごとを巻き取ると聞きます。では面倒ごととはなんなのでしょうか?
人の数だけ悩みがあると思いますが、コーダーとして何ができるのでしょうか。
全体を見て立場を知る
面倒ごとを巻き取りたいのであれば、まず自分の位置と全体の地図を知るべきです。
建物を建てるにしても、配管屋だけでも消火、衛生、空調、冷媒、ガス..。建築にしても土木、鉄骨、基礎、内装といった「建物」として成立する為の無数の工程があります。建築業界にはスーパーゼネコンが存在し、大成建設や大林組、鹿島建設といった会社が多くの建物を建てており、その他にもマンションなら長谷工や中小企業がいて、そこから設備会社などにお金が流れてきます。
ではweb制作とは何業界なのか?
webサイト制作は誤解を恐れず言えばおおよそ広告業界だと考えています(特にLP)。よって元をたどれば制作会社さんはお取引会社の名に広告代理店最大手の電通を記している事が多くあります。
世の中に告知する施策の一つとしてwebサイトがあり、それを専門とする制作会社があります。
動くだけでは意味がなく、結果を出す為には業界ごとの専門知識や機能が必要です(ノウハウとコンテンツの違いみたいなもの)。そのため星の数ほど業界専門知識を持った制作会社があります。
制作会社の中でも、コーダー<デザイナー<ディレクター<マーケター<経営者と言った層があります。
全体を見れば建築業界と同じくそれぞれの専門職がいる筈です。その人に任せた方が良い結果が出る。
するとコーダーとしては半端な付加技術をアピールするより、「とにかく実装関係は悩まないで任せて」といったポーズをとることになります。ディレクターのやる事が多岐に渡るように、コーディングとその周辺だけでも確認すべき事は無数にあります。
コーダーとしての案件ごとの実装経験値
デザイン通りにコーディングできても、実際には多くの問題があります。
SEOはどうするのか。演出はどうするのか。この部分は編集可能として実装したいのか?
WordPress制作なら、管理画面で毎日管理する人の手間を減らせているか?
レスポンシブしたら見づらい、触りづらい部分はこのまま実装すべきなのか?
作業を進める中、デザイン上で意図のないズレに気づいたら、初稿の時に報告すべきか?
一つ一つ聞いている訳にもいかないので、事前に肝心なところは確認し、細かい部分に関してはおおよそ常識だろうという形で仮実装して、まとめてお伺いを立てる事になると考えます。
このコーダーとしての実務実装経験値から、先読みや連絡の手間に大幅な差が生まれると考えています。
極論「わかってる範囲で説明して任せたら、自動的にいい感じで納品された」がコーダーとして理想でしょうか。
あまり表に出ない現場経験という情報
スプリンクラーでも図面と合わないといった事はよくあります。図面の意図を読んで「こういう意味でしょ」と対応する事があります。( 間に合えば確認取りますし、変更箇所は報告します )
単に配管と言っても建築現場ごとに様々な違いがあります。新築と改修工事、老人ホームと病院と学校、マンションとデパート、大企業ビル、地方と都内、大手ゼネコンと中小ゼネコン、それぞれ悩みは違います。これは座学では知る事ができません。
同じように、LPかコーポレートサイトか、ECサイトか、どういう業界のサイトなのかでよりよくする方法は違う筈です。これも、同種のサイトを作った事がある人とない人では先読みできる部分が違うと考えられます。
結果が出したいならそれぞれの専門家がすべき
基本的には、SEO対策や本格的な演出デザインなどはそれぞれの専門家が中心となって決めるべきです。本当に結果を出したい場合にコーダーに内容までよしなにさせるのは、コーダーの責任とは考えません(実装周りはします)。
コーダー自身でも知りうる限りの基本的な設定は盛り込み「とりあえず機能的に問題ない」風にはしますが、多くの場合は専門外でしょう。
逆に簡単なLPであればデザイナーの方がコーディングまで担当してしまうのも良いですが
やはりコーダーが行った方が、高度な演出の実装や、WordPressの機能や管理画面を扱いやすく改造したりすることに長けています。
消火配管の手が足りず、衛生配管屋が応援に来たことがあります。パッと見早いし配管もできているのですが
細かい支持の取り方などルールが違って「それちょっとまずいんじゃない・・」となる事がありました。衛生配管のプロであって消火のプロではないのです。それは後からそっと直しました。
実務経験が少ない人はどう価値を出すか
実務経験値が価値なのであれば、本来就職して先輩方に鍛えられるのが自然でしょう。実務を知り経験し、それから独立。フリーランス=一人親方は、本来そういうものです。
しかし就職した場合でも、いざ独立すれば営業から案件の打ち合わせ、お金のやり取りまで経験のないことばかりです。結局未経験でも勉強しながらやらなければならないのです。また、1年も経てば技術は変わってきます。結局自ら学ばなければ生きていくことは難しいです。
実務経験が少ない=確信的に即答できる経験が少ない状態で、選ばれる価値を出すことは、事実難しいです。
しかしまず仕事の枠組みを理解した上で、地道に求めらる事を日々学び、縁が在った方には誠実に全力でご対応する事で信頼を積み上げていくしかないと考えております。
「仕事」を考える上で、設備屋の職長経験は今生きていると実感しております。
まとめ:設備屋時代の経験からコーダーとして活かせること
問題が現れた時真価が問われます。逃げるのか、こなすのか。
その為には裏付けされた自らの学び・経験が必要です。
作業と仕事を分けるのは、経験値だけではない。
より良い結果を出すため、お互いの知見をすり合わせる事です。
コーダーはあくまでコーダーです。しかしその中でも視野は広く持ち、実装に関する事はお任せいただけるようにしていきます。
まとまっていないようですが、他業種からweb制作者になられる方がたくさんいる中、
前職とweb制作を比較して、どういった気づきや共通点があったかという意見はあまり見ない事から
書き連ねてみました。